【節税対策】不動産投資は節税に「なります」👉その理由とは❗️❓🏡💰|不動産ラボ
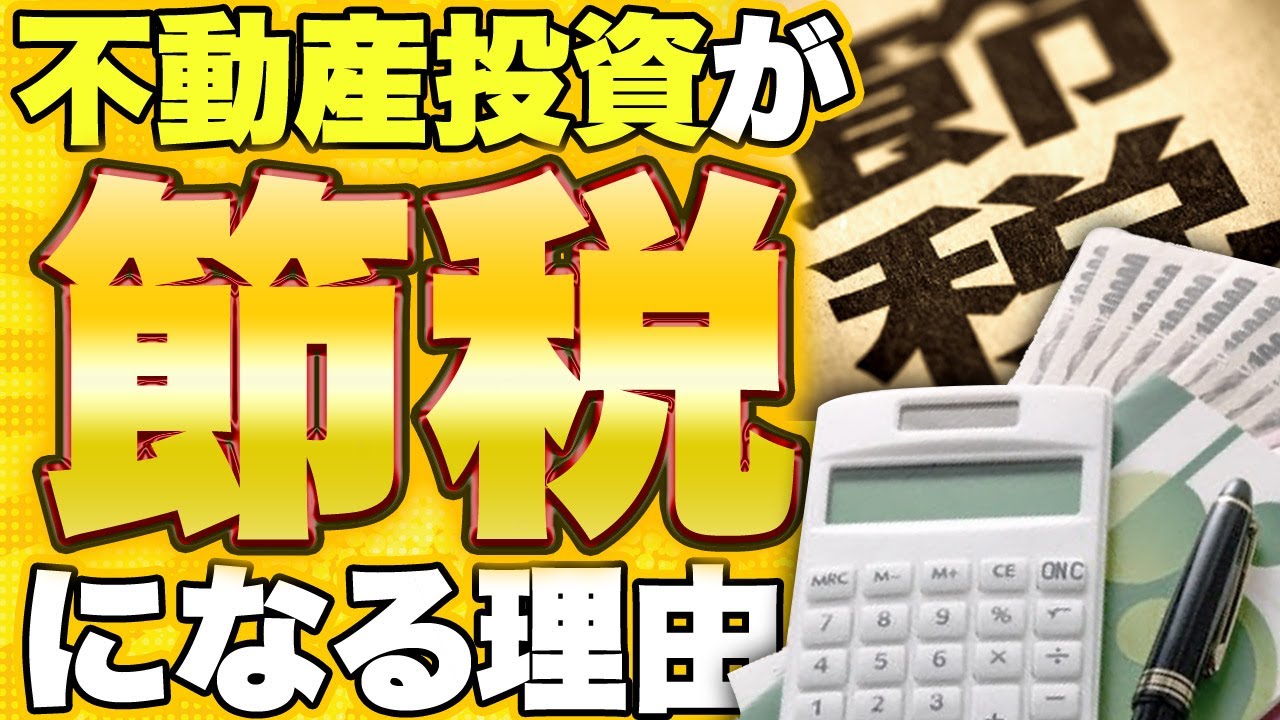
#不動産投資 #不動産節税 #不動産ラボ
「不動産投資が節税対策になる」…、そんな魅力的な言葉はよく耳にしますよね。不動産投資は経費にできる部分が大きければ節税できるということですが、その仕組みがよく分からないという人もいるでしょう。それに、「減価償却」という聞き慣れない言葉も出てきます。
不動産投資は誰でも節税ができるというわけではなく、人によっては節税できない人もいると言われています。
今回は、不動産投資が「なぜ節税になるのかというカラクリ」に迫ってみましょう。
■不動産投資で節税はできる?仕組みについて理解しよう
不動産投資で節税できるとすれば、所得税や住民税、そして相続税や贈与税です。それぞれについて、ひとつずつ仕組みを解説していきます。
◎所得税と住民税の節税効果とは
不動産所得で赤字が出た場合、勤め先からの給与所得の部分からも差し引くことができます。それが「損益通算」というものです。
つまり、不動産投資で経費が増えて赤字になったときは、そのマイナス部分を給与所得から差し引くことで、課税部分を少なくできることになります。そして、結果的に所得税をおさえることにつながるというカラクリです。
例えば、600万円の給与所得があり、不動産投資で100万円の赤字が発生したとします。600万円から100万円を差し引くことで、課税対象は500万円になります。
所得税が減れば、住民税の所得割が少ないとなるため、両方の税金をおさえることができるでしょう。
◎相続税と贈与税の節税効果とは
相続税の場合、「現金」か「不動産」という相続するものの種類によって、評価額が異なります。
例えば、現金を相続すれば、そのままの価値の評価額です。一方、土地、建物などの不動産は、路線価や固定資産税評価額となり、7~8割まで税額をおさえることができます。
このため、現金で相続や贈与するよりも、同じ価値の不動産の方が税金は低くなる…つまり、節税できるという考え方です。
■減価償却費が経費節減のポイント
不動産投資では、初めに「物件を買う」という大きな初期投資が必要です。まずは物件購入に費やした金額を経費にしたいと考えるかもしれません。
しかし、そのすべてを一回で経費にはできず、長年にわたって少しずつ計上しなくてはなりません。そこで用いられるのが「減価償却費」です。
建物は年々劣化するため、価値が少しずつ下がっていきます。実際にお金が出ていくわけではありませんが、資産価値としては低くなるという状態です。
つまり、減価償却は「帳簿上で年々価値が下がっていく分を経費にできる」というもので、節税には繋がるという仕組みです。
毎年、経費に計上できる額は、償却期間から算出します。償却期間は、鉄筋コンクリートや鉄骨、木造などの「建物の構造の種類」や、「新築なのか?中古なのか?」によっても異なります。
償却年数は、中古物件の場合なら、
(法定耐用年数 - 経過年数)+ 経過年数 × 20%
という算式にあてはめて求めることができます。
償却期間の間はずっと経費にすることが可能です。
同じ金額を毎年経費にできますが、初年度はそのほかにも計上できる大きな経費があり、マイナスとなるケースも多いです。さきほどお伝えしたように、損益通算すれば、所得税や住民税が減らせる可能性が高いでしょう。
ただし、すでに所得税や住民税が給与所得から支払われているため、税金を還付してもらうためには確定申告でしっかりと手続きをすることが大事です。
■経費にできるのはどんなものか
次に、どんなものが経費にできるかについてです。
◎初年度の経費について
不動産投資を始めるには物件を購入しますが、購入時には諸費用が結構かかります。
そのうち、不動産取得税や登録免許税、司法書士費用、ローン事務手数料、印紙税などを経費として申告できます。これらの諸費用に加え、減価償却費などの経費もプラスします。
不動産収入よりも経費の方が多く赤字になれば、ほかの収入からも差し引くことができる損益通算を使って節税しましょう。
◎主な経費とはどんなものか
せっかく経費にできるのに申告しなければ、節税につながらないこともあります。申告できる経費の種類をおさえておきましょう。
減価償却費以外に経費にできるものは、
・固定資産税や都市計画税などの税金
・マンションなら管理費や修繕積立金
・不動産投資ローン返済時の利息
・火災保険料や地震保険料
・物件で壊れた箇所があればその修繕費用
・管理を委託した場合の費用
・不動産投資に関連する連絡手段となるスマホ利用料やインターネット回線利用料
などです。
費用がどのくらいかかったかをしっかり計上するために、領収書はもちろん、支払い日や金額についても記録しておきましょう。
■節税ができないパターンとは?
お伝えしたように、不動産投資のすべてのパターンで節税できるわけではありません。その違いは、どんなものなのでしょうか。
◎どんな人が節税できるか
そもそも所得が多く税金をたくさん納めているという場合は、節税できる可能性が大きいです。
不動産投資を始めるために高額物件を買えば、減価償却費として経費計上できる部分も増えます。所得が多い人は、投資物件は1つだけに限らず、複数所有しているパターンもあるでしょう。それに比例して、税金が還付される金額も増えるかもしれません。
◎節税にならないのは小規模な投資物件を買った人
副業として不動産投資を始める人も多くなっています。「節税できる」と言われて始める人もいるかもしれません。
ただ、ワンルームマンションのように、少額で買える物件を購入した場合、ほとんど節税効果はないでしょう。確かに、1年目は購入のときに諸費用が多く赤字にできるので、税金はおさえることが可能です。
ただ、次の年からは大きな経費は見込めず、結果的に節税効果はないでしょう。
■節税を期待する前にチェックしておきたい注意ポイント
不動産投資に「節税効果」を期待している場合は、まずは次の注意点をおさえておきましょう。
◎節税効果は初めの年だけのケースがほとんど
購入時に諸費用がたくさんかかるため、不動産投資の初年度は節税の効果が感じられます。ただ、翌年からの経費を計上しても、赤字にできるほどかからないのがほとんどです。
また、空室が続いて「家賃収入がゼロ」になれば、赤字になり課税所得を減らすことができますが、節税はできても、不動産投資の本来の目的である「収入」が減っている状態です。収入を増やしたいと始めた不動産投資が、「損」を生んでいるとう事実を考慮しなければなりません。
◎控除額は青色申告の方が多い
不動産投資で行う確定申告には、「白色申告」と「青色申告」という種類がありますが、青色申告には「青色申告特別控除」があり、55万円、もしくは10万円を控除することができます。
「マンションやアパートなら10部屋以上ある」「戸建てなら5棟以上」と、規模の大きい不動産投資で受けられるのが55万円の方の控除です。
ワンルームマンションのように規模が小さければ10万円の控除をすることが可能です。
ただ、この控除はすでにマイナスの所得になっていれば、損益通算することはできません。
例えば、ワンルームマンションを所有していて10万円の青色申告特別控除が使える場合についてです。
減価償却費やそのほか計上できる経費を差し引いて5万円の所得だとしましょう。この場合は、5万円を控除した時点で所得がゼロになるため、10万円の青色申告特別控除で使える控除額の上限が5万円ということになります。
■まとめ
「節税効果がある」と言われると、不動産投資を始めたい気持ちになる人もいるかと思います。しかし、今回お伝えした内容のように、節税できないパターンも多いのが現状です。
不動産投資を始める前には節税効果があると言われるカラクリについてはじゅうぶんに理解しておく必要があります。
YouTube