給付付き税額控除とは何か?メリット・デメリット・消費税減税阻止の言い訳?
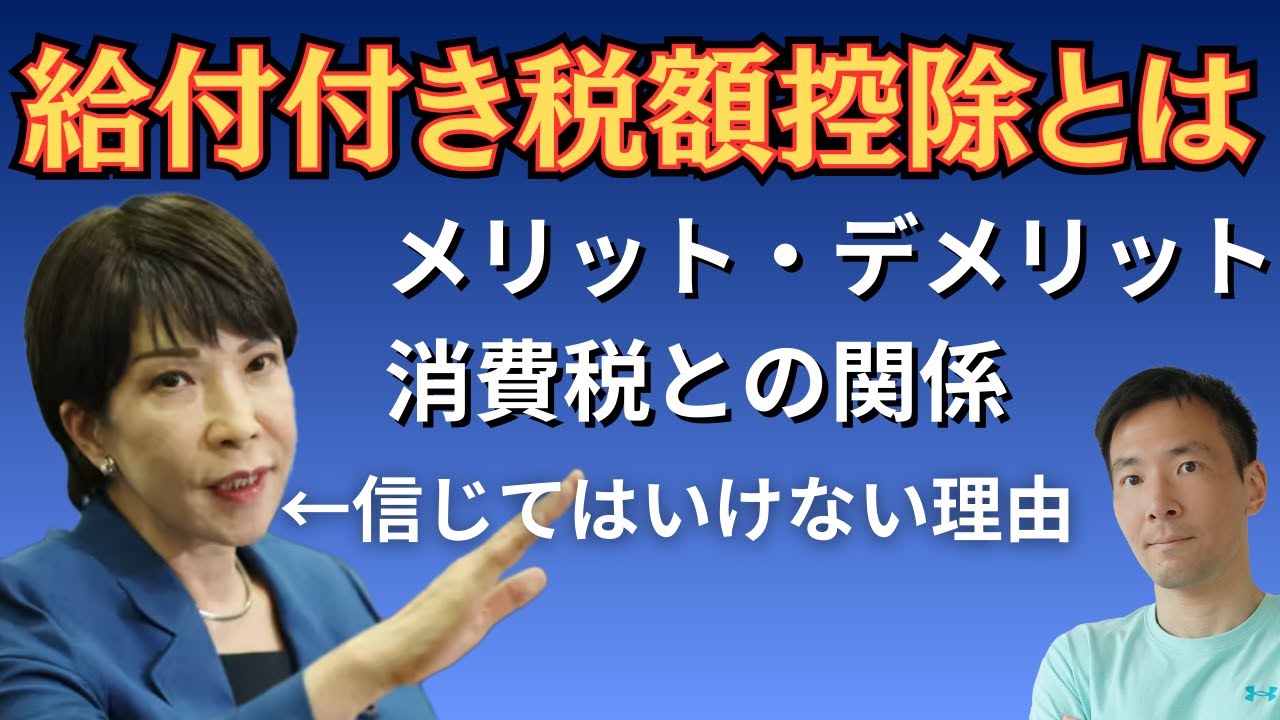
給付付き税額控除とは
自民党総裁選で、高市さんが給付付き税額控除の制度設計を進めると明言
また、自民・公明・立憲の3党で、給付付き税額控除の議論をすすめようという話が出ている
そもそも給付付き税額控除とは何なのか?
メリット・デメリット・消費税との関係、知っておくべき注意点などを考えてみる
■給付付き税額控除とは
税金の軽減と低所得者への社会保障を一体化した措置
控除とは、税金の納税額とか税金を計算するための所得額から、一定の金額を差し引くこと
税金の軽減措置
たとえば所得税を10万円控除とする場合、
本来の納税額が16万円の人は、16万から10万円が控除されて納税額は6万円となる
ここで問題になるのは、本来の納税額が10万円以下の人
本来の納税額が9万円の人も1万円の人も、一律で納税額が0円になる
納税額9万円の人は9万円得したことになるが、1万円の人は1万円しか得していない
納税額が低い、非常に低所得の人ほど、行政からの手当が少ないという不平等が起こってしまう
そこで、控除だけでなく、給付を組み合わせる
本来の納税額が9万円の人には、9万円控除+1万円給付
本来の納税額が1万円の人には、1万円控除+9万円給付
これで全員10万円得したことになる
これによって、低所得者への支援を充実させて、
所得の再分配機能を強化するための措置が、給付付き税額控除
■低所得者への支援を充実させながらも、勤労意欲を削がない
働くよりも、社会福祉にありつく方がいいという状況を作らない
控除と給付の制度設計を上手くやることで、勤労による収入と給付による収入を組み合わせて、
常に働いたほうが総手取りが増えるような制度にしてく
所得が増えるほど給付は減るが控除が増えることで、手取りは増えていく
一方で、所得が一定ラインを超えると、控除がなくなって所得税額が増えていくので、応能負担の原則に叶う
それでも、控除がなくなって手取りが減るようなことが起こらないように、
常に、働けば働くほど手取りが増えるような設計にしていくことができる
■日本においては、消費税の逆進性への対策として導入が検討されてきた経緯がある
消費税の逆進性
税金の原則は、本来「応能負担」であり、払える能力に応じて払ってもらう
だから、所得が多くて余裕がある人ほど、税率が上がっていく累進課税がある
しかし消費税は、所得に関係なく平等に使った分だけ一定割合で課税される
応能負担の原則から言えば、平等だからこそダメ
しかも消費税は生活必需品にも容赦なく課税される
金持ちも貧乏も同じ人間なんだから、人間が最低限生きるために必要な支出はあまり変わらない
となると、所得が少ない人の方が、所得に対する最低限の支出の割合が大きいので、
そこに課税されると所得が少ない人ほど実質的な負担感が大きくなる
消費税は、この逆進性が構造的な問題として常につきまとってきた
消費税の逆進性を緩和するために、給付付き税額控除を導入する場合
2012年に国会での議論でも用いられたグラフ
所得階級別消費税負担割合を見ると、年収200万円以下の低所得層が、一番所得に対する消費税の負担割合が大きく、
2000万円以上の高所得層が、一番負担割合が少ない
食料品への軽減税率を適用しても、高所得者も食料品は買うんだから割合は変わらない
つまり軽減税率は、消費税の負担軽減にはなるけど、逆進性の軽減にはならない
そこで、消費税負担を軽減するための給付付き税額控除を導入すると、低所得層ほど給付額が大きくなるので、逆進性が大きく緩和される
ただし、今度は年収300~400くらいの層が一番負担割合が大きくなって、高所得層ほど低くなっていく
だから、消費税だけじゃなく所得税や他の税制や社会保障も全部巻き込んで、非常に詳細な制度設計をしていく必要がある
■デメリット
とにかく、制度設計の複雑さと、実際に実行するための行政負担が膨大であること
低所得者とか子育て世帯への支援を充実させながらも、勤労意欲を削がないように
所得が増えるほど手取りが増えていくような、制度設計を入念にする必要があること
諸外国で特に問題になるのは、行政負担の増加・不正受給への対策
日本の場合は特に、これまでは低所得の非課税層は、単に非課税であるだけなので、詳細が把握されてこなかった
非課税とは言っても、
所得が10万円なのか90万円なのか
所得がないけど、実は資産があるのか
所得がないけど、実は近所の親族から援助を受けてるのか
こういった事が全然把握されてこなかった中で、公平性のある給付付き税額控除をやるには、この低所得層の実態把握という
とてつもない行政負担が生じる
それだけじゃなくて、今までの課税は個人単位だったけど、給付は世帯単位で行われるとすれば、
世帯の正確な所得を把握しなきゃいけなくなる
父・母・子がそれぞれ働いて所得がある場合に、同一世帯なのか別世帯なのかを判別することも必要
韓国では、給付付き税額控除を導入する際に、税務当局の職員を10%増員したらしい
それだけのコストを払ってやるのは、その他の部分で行政コストを削減できるから
つまり現行の児童手当とか生活保護とか失業保険とかの社会保障を、全部給付付き税額控除で一本化することで、
社会保障と公平性の担保を実現できる
だから給付付き税額控除とは、本来はものすごく大規模な範囲で、社会保障の整理とか、税と社会保障の一体化改革とか、
そういった大きな視点での議論が必要で、制度設計にもかなりの時間を要する議題
■しかし現在の日本では、どういうわけかそうではない
高市さんの発言とか、いま自公立の3党で進んでいる話し合いをみても、
目下の物価高対策とか、消費税の逆進性軽減とか、そういった短期的な視点での議論が先行している
特に問題なのは、この給付付き税額控除が、消費税を減税しない言い訳として進められていること
消費税の大きな問題は、逆進性だから、逆進性を緩和するための給付付き税額控除を導入すれば、
消費税を減税しなくてもいいでしょという流れになるし、
そもそも給付付き税額控除をやるための財源が必要になるので、消費税率自体は上げられる可能性がある
消費税率を上げても、低所得層には給付付き税額控除があるんだから良いでしょという流れに持っていかれる可能性が高い
いまの自民党・高市さんなどは、目下の物価高対策として、消費税減税をやるのは、
実現までに時間がかかるから現実的ではないと言い訳している
その対案として給付付き税額控除を出してきたわけだが、給付付き税額控除の方がはるかに時間とコストがかかることは明らか
これを言ってくるということは、高市さん自身がこの内容を全然わかっていなくて、官僚の言いなりになっている可能性が高い
■消費税なんて、徴税停止すればいいだけ
インドは1ヶ月で消費税減税を実現させた
しかも今は軽減税率の仕組みがあるんだから、軽減税率で全品目0%にすればいいだけ
やろうと思えばすぐにできる
消費税については、以前の解説動画があるのでぜひ見て欲しい
根本的には、消費税は消費者ではなくて事業者に課せられる税金であるということ
そして事業者に課せられるからこそ、皆さんの給料を直接的に奪い取る税金であるということ
さらに消費税の逆進性は、消費者視点だけじゃなくて事業者視点でも非常に大きいということ
低所得の消費者への軽減措置は、給付付き税額控除で出来るかもしれないけど、小規模事業者の軽減措置には、全くならない
消費税は、小規模事業者ほど負担が大きくて、誰もが知ってるようなグローバル大企業は、
一円も納めてないどころが、何千億円も還付されている
だから消費税の逆進性という問題は、実は消費者よりも事業者にとっての問題
大体にして、消費税は逆進性があるから、わざわざ給付して軽減措置をするくらいなら、最初から消費税なんてやめれば良いじゃないの
■小泉進次郎が、2030年までに平均年収100万円増やすとか言ってるが
賃上げは、政府じゃなく民間企業がするもの
政府が上げられるのは公務員の給料だけ
民間の賃金を上げるためにできるのは、財政措置だけ
民間の賃金を上げるために政府ができる最も効果的な方法は、消費税と社会保険料の引き下げ
この一番大事なところから、逃げてんじゃねーよって話
■まとめ
給付付き税額控除は、低所得への支援を充実させながらも勤労意欲を削がない、公平感を担保できる制度としてのメリットはある
さらに、児童手当とか失業保険とか生活保護とかと一元化して、社会保障をスリム化できる可能性もある
そういう意味でポテンシャルの大きな制度なので、検討の価値は十分にある
しかし、その制度設計の複雑さと行政負担が考えると、短期的には実現不可能で、数年単位での入念な議論を必要とする
目下の物価高対策としては、どう考えても不適格
ましてや、消費税減税をしない言い訳として持ち出すのは、明らかにおかしい
よって、物価高対策とか消費税減税をしない言い訳として給付付き税額控除を持ち出す政治家は、絶対に信用してはならない
いまのインフレは世界的な現象だから、日本がどうこうしても物価上昇自体を抑えるのは難しい
となると、日本がやるべきなのは賃上げ促進と手取りを増やしてインフレのダメージを軽減すること
そのためには、減税しかない
給付付き税額控除なんて、小難しい議論に惑わされないことが大事
国民が正しい知識を持って、政治にプレッシャーをかけていこう
#消費税
#給付付き税額控除
#インフレ対策
YouTube